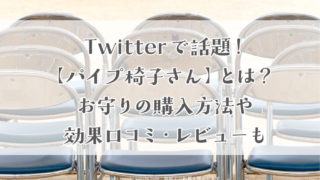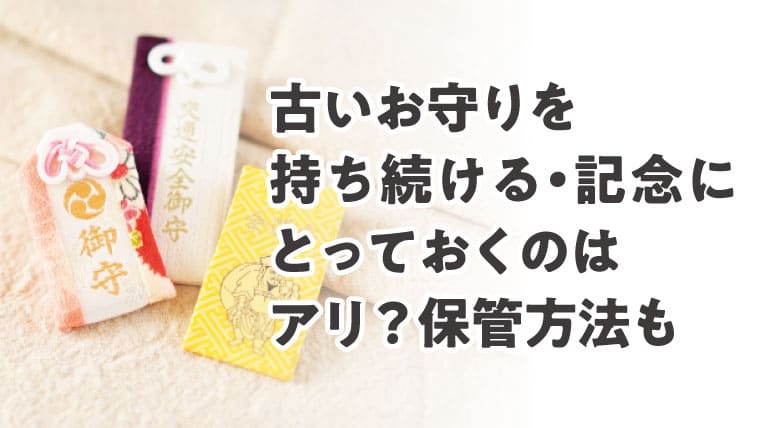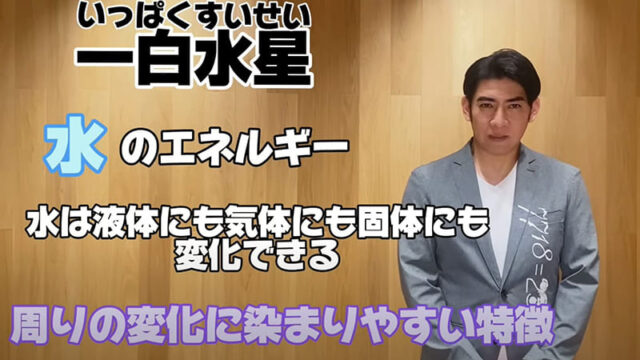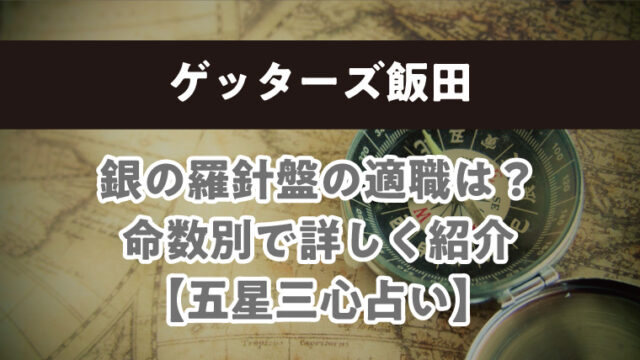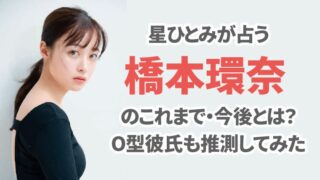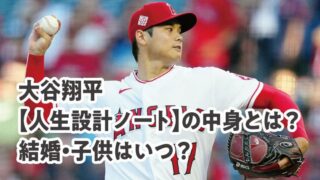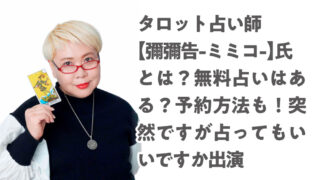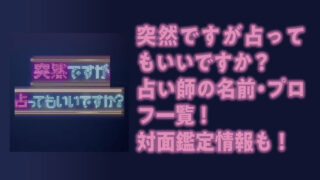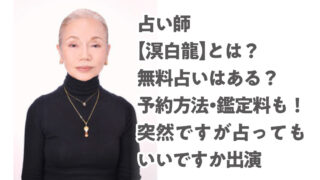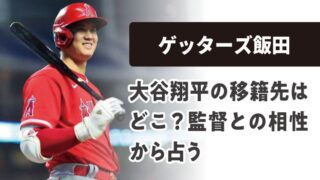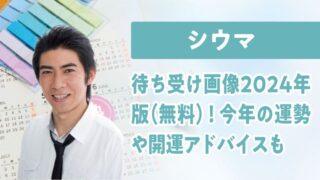初詣や交通安全などの日常から受験や出産などの節目のイベントまで、人生の中でお世話になることも多いお守り。
そんなお守りの効果は一般的に1年といわれています。
しかし「人からもらって思い入れがある」や「遠方の神社のお守りで、なかなか足を運べないから持っていたい」、「思い出として、記念にとっておきたい」など理由は様々ですが、思い入れがあって手元に置いておきたい人もいるのではないでしょうか。
今回はそんな古いお守りを持ち続ける・記念にとっておくのはアリ?なのか、保管方法もまとめました。
古いお守りを持ち続ける・記念にとっておくのはアリ?

古いお守りを持ち続ける・記念にとっておくのはアリ?なのでしょうか。
答えは〇。思い入れがあれば「アリ」です。
基本的には、お守りの効果は1年です。
諸説ありますが、鎌倉時代に伊勢神宮からの遣い人が全国をまわり、古いお札を回収すると同時に新しいお札を配っていたのが1年という期間だったことに由来すると言われています。
※お守りによっては期間が異なるものもあります。
また、お守りには神様が宿るよう祈願された内府(ないふ)という神の札が入っています。1年を過ぎると穢(けが)れが溜るので、それを返納し、新しいお守りを授かることで浄化ができ、効力が続くとされています。
よって本来ならば、1年ごとに古いお守りを返納し、新しいお守りを授かるのが良いとされています。
ただ、人からいただいたいて気持ちがこもっていたり、愛着のあるお守りについては、この限りではありません。その場合は、乱雑に扱わず大切に保管しておくことが重要です。
乱雑に取り扱ったり、どこかに放置してしまうようであれば神社に返納するのが良いでしょう。
ちなみに、これまで1万社以上の神社に参拝してきた神社ソムリエの佐々木優太さんによると、お守りには神様が宿るもの。定期的に新しくすることで、宿る神様が元気な状態を保てる「常若(とこわか)」という考えだそう。
とはいえ、いただいたお守りなどは「常若」の考え方より、自分が「持っていたい」という感情を大事にしてほしいと話しています。
古いお守りの保管方法は?
それでは古いお守りの保管方法はどうすればいいのでしょうか。
お守りを身につける場合
お守りとして持参したいなら、バッグやお財布、車など自身と共に行動できる場所に付けるのが良いでしょう。
お守りを自宅に保管する場合

自宅で保管する場合は、神棚が良いとされています。
神棚がない場合は南または東向きで、できれば高い位置に置くのが良いでしょう。
神様が宿っていると思い、ほこりがかぶらないようこまめに掃除をするなど気を配りましょう。
まとめ
神様が宿るお守りは、通常1年といわれていますが、特別なお守りなら返納するしないは個人の自由。
手元に置いておく場合は、大切に取り扱いしましょう。
関連記事:神社ソムリエ・佐々木優太とは何者?2023年おすすめの神社も

関連記事:願いが叶う?!【パイプ椅子さん】とは?待ち受け画像(お守り)の購入方法や効果口コミ・レビューも